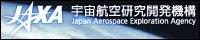大学受験を成功に導くアルファ・ネクサスの家庭教師は
ALPHA NEXUS
例えば数学、物理、化学、生物などの理系科目担当と英語、国語、小論文などの文系科目担当に分かれながら、大学受験の全てに対応。『他社とは一味違う切れ味と人間力』で生徒さんを志望校合格に導くプロフェッショナルです。
家庭教師アルファ・ネクサスでは、共通テスト(大学入学共通テスト・旧センター試験)の全科目対策はもちろん、東大、京大をはじめとする国公立大学の二次試験や早稲田大、慶應大をはじめとする私立大学の数学、英語、国語(現代文、古文、漢文)、物理、化学、生物から日本史、世界史、地理、現代社会、倫理・政経、小論文、総合型選抜(AO入試)、推薦入試、内部進学対策まで、生徒さんの習熟度に応じて的確な学習プログラムを立案し、幅広く対応できる
▶おすすめの家庭教師をご紹介しています。
当社は完全後払い制です(月末締めの翌月払い・入会金・諸経費なし)
▶総合型選抜(AO入試)・推薦入試コースはこちら
また、例えば数学ⅠⅡⅢ・ABCや情報ⅠⅡなどの新課程にも適宜対応しておりますので、ご安心ください。
大学受験を担当する当社の家庭教師陣は、豊富な経験に裏打ちされた知識と独自のメソッドを駆使。生徒さんの個性を最大限に引き出しながら大学受験の全ての分野で的確なサポートを実施し、志望大学合格に導いています。
▶無料体験授業はこちらから。
▶オンライン家庭教師コースでの大学受験対策も大変好評です。▶15秒テレビCM オンライン編
大学受験コースの概要
家庭教師アルファ・ネクサスの▶家庭教師は大学受験の共通テスト(大学入学共通テスト・旧センター試験)の全科目対策はもちろん、国公立大学の二次試験(小論文を含む全科目)や私立大学の数学、英語、国語(現代文、古文、漢文)、物理、化学、生物から日本史、世界史、地理、現代社会、倫理・政経、小論文まで幅広くサポートしています。
外部リンク
▶令和8年度大学入学共通テスト(本試験)平均点等一覧(中間集計)
■河合塾:▶2026年度 大学入学共通テスト速報 ▶バンザイシステム・ボーダーライン一覧
■駿台・ベネッセ:▶データネット2026 ▶インターネット選太君
新課程2年目となり初年度の平均点調整や様子見から状況が変わって問題の分量やひねった設定が増えたりして難化傾向にあり、全体平均点も大きく下がりました。
例えば情報は難化し、初年度は高めだった平均点も、2年目からはプログラミングやデータ分析、身近な情報技術などに対する深い理解を問う問題が標準化され定着する見込みです。
全教科を通じて、単一のテキストではなく、複数のグラフ・図・対話文を組み合わせて解答を導くスタイルも多くなりました。今後は多角的視点から解かねばならない問題がより主流になると考えられます。
🔽宇宙余話 受験生の気分転換にどうぞ
【数学ⅠA】
やや難化か難化。
・複雑な問題設定に対して丁寧な誘導が付され、その誘導を応用してさらに別の問題を解くという形式の問題が多く出された。
・「集合と論理」の問題が珍しく本格的に出題され、誘導問題も増え解答に時間がかかった受験生も多かったのではないか。
・新課程で追加された「期待値」「仮説検定」といった分野からの出題はなかった。
・試験時間に対して問題の分量が多かった上に図形と計量や二次関数等で捻った問題も見られ、今後も出題者の意図を短い試験時間の中で素早く読み解く力が問われるものと考えられる。
【数学ⅡBC】
昨年並か。
・数学ⅠAと同様に、誘導をもとに基本から応用まで幅広いレベルの問題を解く形式が多かった。
・例年出題されている「指数と対数」からの出題はなかったが、証明(公式の穴埋め)が出題された。今まで見られた身の回りに関連する問題は減少傾向。
・第7問では前年出題がなかった「平面上の曲線」からも出題され、「複素数平面」との融合問題となった。
・応用問題については受験数学の典型問題といえる内容が多く、成績上位層にとっては得点しやすかったと考えられる。ただし今後は共通テスト特有の、身のまわりの現象や社会生活に関する問題も出題される可能性が十分あるため、対策は不可欠である。
【物理】
やや難化か。
・多くの問題は前年よりもシンプルな設定だが、典型問題とは少し異なる形になっており、本質的理解に基づいた考察を要する問題(知識があるだけでは解けない)であった。探究関連の問題はなし。
・直感に頼りすぎると間違えやすい問題が多く、いろいろな問題設定に関する確かな理解をもとに適切な数式を用いて、現象を冷静かつ慎重に見究める力が問われた。
【化学】
易化か。
・思考力を試す問題が減り前年から大幅に易化。典型的な問題が多く出題された。
・新課程の内容である「エンタルピー」からは、選択問題が1題だけ出題された。
・難易度設定がまだ不安定であるため、鉄板の問題集に載っていないものも含め、今後もいろいろなレベルの出題に備えて理論・無機・有機をバランスよく学んで対策しておくべきである。
【国語】
やや難化か。
例えば本年度の第2問は遠藤周作「影に対して」からの出典だったが、時代背景を感覚的に理解できない受験生が多かったのではないか。「戦後以降の文章」といっても既に80年程度の開きがあるため、受験生にとっては既に大昔であるためか昭和初期の時代背景を理解できない受験生が非常に多かったようだ。普段から教養として昭和期に書かれた名著や名作映画を見慣れておくことも重要になる。
現代文
・第1問:約4000字を超える(昨年より500字程度増えた)芸術に関する評論。問題文自体は読みやすいが、文章量が増えたことや設問が紛らわしい等で時間配分に戸惑った受験生も多かったのではないか(設問数は昨年同様4つだが難化)。
・第2問:本文に対する批評とそれを纏めたノートから出題。文字数は昨年と同程度で読み難いものではないが、「ノート」と「生徒の対話」がやや難解。
・第3問:簡単な資料(グラフはなし)を使って考えさせる新課程らしい問題。分量は昨年並。昨年から追加された問題であるが、昨年とは異なり、量的調査の読み取りではなく質的調査の読み取り問題であった。そのため設問も抽象的で、混乱した受験生も多かったのではないか
古文
・平安時代の「うつぼ物語」からの出題。源氏物語以前の文章で、文章の読み慣れなさから平均点が下がってしまった可能性あり。しかし、内容、設問共に基本的なものが多く、単語力と文法力(特に敬語)をきちんと身につけてさえおけば対応できるものばかりである。共通テストになってから、擬古文等、時代が下ったものが多く出題されてきたため、中古の作品への対策を怠った受験生が多かったことも影響したか。
・本文の分量は昨年と変わらないものの本文が1つとなり和歌もなかった。問5は本文と同一作品の別の箇所(本文より後)が引用されており、複数の古文と複数の登場人物を正確に読み解く力が要求される内容だった。
漢文
・今年も日本の漢文からで江戸時代後期の漢学者・長野豊山の詩論「松陰快談」からの出題となった(漢詩はなかった)。
・否定形、使役形、詠嘆形といった基本句形と各段落の内容を正確に把握できているかを問うもの。その他は内容説明、語釈、書き下しなどで分量も昨年並だった。
問6・7は少し難しかったものの、他は極めて基本的な問題。漢文は例年並みの難易度であったと言える。
【英語】
リーディング
やや易化か。
・昨年同様、全大問が読解形式であった。
・題材は日常的な文章から説明文まで様々なものが扱われた。
・設問では、昨年見られなかった新形式の問題も数問出題され、出来事の順序を問うものやプレゼンテーションのスライドを完成させるものなどが出題された。
・多角的視点から情報を処理する力が求められ、昨年に続き読解問題を通じて英文を組み立てる力を見ようとする意図が感じられる。
第1問
ダンスクラブのメンバー同士がコンテストの衣装について意見を述べているやり取り(テキストメッセージ)を読ませる問題。基本的な読解力を見る内容だが,設問の英文を「正確」に読み解かないと正解できない。
第2問
「キャンパス内にある寮の満足度調査」についての大学側の公式見解と学生(利用者)の声を読ませて内容を整理させる問題。互いに異なる見解のポイントを把握できるかが問われた。
第3問
座禅ワークショップで瞑想中に虫が飛んできた体験に関する文章を読ませて3問に解答させる内容。出来事が発生した順序を時系列に沿って正しく把握できるかを見る問題だが、落ち着いて本文を読めばさして迷わないはず。
第4問
エコに関する内容で第三者(教師)のアドバイスを踏まえ、論理的に適切な文章に訂正できる力を問う問題。また、与えられた一文を正しい位置に挿入する新機軸問題も出題された。
第5問
図書館のフェアと推薦図書に関するチラシやオンラインフォーム、図書館からのメールといった資料を読んで答えさせる問題。昨年同様に各資料を正しく且つ総合的に把握した上で推測しないと解けない。
第6問
おにぎり店の店主と中学生(剣道部)の物語を読み、全体像を把握させて空所補充させる問題。
思い出話の時系列を把握できればさほど難しくはない。
第7問
昨年のプレゼン用メモの空所補充問題から今年はmind-wandering(心の迷走)に関する記事を扱った問題となった。新しい形式であり専門用語も出てくるが、順番通りに読んでいけば自ずと解答できる内容。
第8問
スポーツと技術の進歩に関する複数の見解と資料を読ませた上で、それぞれ異なる立場からの視点を正確に把握できるか問う問題。
複数の論点を整理する力と共通項の抽出力を試す問題(ちなみに3個の空所を正しく埋められないとステップ2の正確に辿り着けない形式は昨年と同じ)。
リスニング
やや難化か。
語彙レベルと語数は昨年とほぼ同じで、求められる技能にも変化無し。
第1問
A:短い発話のその内容と最も近いものを選ばせる。発話内容から状況を掴み取る要点把握力が問われた(第1問では馴染みがない単語に戸惑った受験生もいたようだ)。音声は2回。
B:Aと同様の出題。発話内容の要点把握力に加え語彙力も求められた。音声は2回。
第2問
日常に関する短い対話。場面の説明と絵を参考にするものだが、各場面が日本語で書かれているため、それが手助けになったはずだ。音声は2回。
第3問
日常に関する短い対話。こちらも日本語で書かれたものを参考にした上で要点把握力を試す問題。複数の要素から正しい判断ができるか否かも問われた。音声は1回。
第4問
A:今年の第4問はイラストの並べ替え問題(昨年はグラフ問題)。
4つのイラストを正しい順番に並べさせるものだが、1枚関係のないイラストが含まれているところが厄介。「同じ選択肢を2回以上使ってもかまいません」という指示も実は関係なかった。音声は1回。
B:4人の話を聴き取る。複数の情報を整理する力が試された。音声は1回。
第5問
海水魚の養殖に関する新たなテクノロジーに関する講義。
講義内容を正確に聴き取り、グラフ情報や学生の話も整理できなければ正確できない。
ワークシートを如何に手早く完成させられるかがポイント。音声は1回。
第6問
A:フランス語の授業に関する対話。
各視点の要旨を素早く把握できるかを問う。音声は1回。
B:電車内など外出中に音楽を聴く時のイヤホン(ヘッドホン)の音量に関する3名の会話。
各立場を把握する力とその主張の根拠となる図表を読み取る力が問われた。音声は1回。
▶ 目次へ戻る
参考:▶大学入試センターのYouTubeチャンネル
家庭教師アルファ・ネクサスのプロ家庭教師は着実に基礎力を養成すると共に思考力、柔軟な応用力を身に着けさせる独自のメソッド(例えば ▶【家庭教師と学ぶ英語】・
▶【英語ワンポイントアドバイス】や
▶【家庭教師と学ぶ数学】・
▶【家庭教師と学ぶ国語】
)を持っており、それらを常に生徒さんの習熟度に合わせて駆使しています。
従って最新の情報に基づいた共通テスト対策はもちろん、東大、京大をはじめとする旧帝大ほかの国公立大学2次試験記述対策から、早稲田、慶應などの超難関私大の記述対策、上智、明治、東京理科、青山、立教、中央、法政、学習院ほかの難関私大の一般入試や総合型選抜(AO入試)、推薦入試まで柔軟に対応することが出来るのです。
▶総合型選抜(AO入試)・推薦入試対策・小論文対策
については大学別にサポートしています。併せて
▶内部進学対策(一貫校フォロー)
も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
大学受験の小論文指導は、当社
▶大学生向け家庭教師コース (
▶特別コース内 )で卒論や大学生のレポート指導に当たっているプロ家庭教師が担当いたします。
大学受験を知り抜いた家庭教師が現役高校生から浪人生、大学再受験生それぞれの状況に応じた合格プログラムを作成し、生徒さんを毎年志望大学合格まで導いていますので、まずは
▶無料体験授業でその実力をお試しください。
▶ 目次へ戻る
■2025年度の新課程入試(共通テスト)の概要について
2025年度の新課程入試は賛否は分かれるものの、正確に課題を読み取り、素早く処理する能力がより問われる内容になると予想されます。但し、今までの経緯、傾向から推すと実際の入試問題は以下のリンク先にあるような「試作問題」よりは易しく解きやすいものになる可能性が高いため、必要以上に怖れることはないと考えます。
家庭教師アルファ・ネクサスでは新課程入試のサポートを全科目で実施していますので、詳細につきましては当社までお問合せください。
▶2025年度(令和7年度)大学入学共通テスト実施日:2025年(令和7年)1月18(土)・19(日)
▶2026年度(令和7年度)大学入学共通テスト実施日:2026年(令和8年)1月17(土)・18(日)
▶2025年度(令和7年度)大学入学共通テストQ&A
※経過措置について
2025年度(令和7年度)の共通テストは新しい学習指導要領(平成30年3月告示)に対応した試験となりますが、浪人生など新教育課程を履修していない受験生に対しては、経過措置として一部の教科・科目(「地理歴史,公民」、「数学」、「情報」)で旧課程科目で受験可。
但し新教育課程履修者は旧課程科目の選択は不可。
▶大学入学共通テスト利用大学情報(都道府県別)
※東京科学大学は東京工業大学で検索
※私立大学の状況については文末参照
*************************************
■数学
※試験時間:60分から70分に増加(それでも時間不足になる可能性大)
○「数学Ⅰ・数学A」または「数学Ⅰ」から1科目選択(試験時間:70分・100点)
分量も増え難化する可能性あり。
○「数学Ⅱ・数学B・数学C」:数B、数Cは各2項目から3項目を選択(100点)
数学Ⅰ・A:「データの分析」、「場合の数と確率」の問題を追加(各20点)
数学Ⅱ・B・C:「数学B」及び「数学C」については,数列(数学B)、統計的な推測(数学B)、ベクトル(数学C)、平面上の曲線と複素数平面(数学C)の4項目のうち3項目の内容の問題を選択となるため、解くべき単元が増えた。
特に「数学Ⅱ・数学B・数学C」を選択する文系受験生の負担が増えることになる。
-----------------------
🔽実際の主題内容について
【数学ⅠA】
・「外れ値」「仮設検定の考え方」「期待値」といった新課程の内容が、試行調査と同様に本試験でも出題されました。
・前年までにみられたような、長い説明文の読み取りにかかる負担はやや軽減されたと思われます。
・立体図形や条件付き確率の正確な理解を要する問題が出題されました。今後も数学の各単元の本質的な理解を問う問題が多く出題されると考えられます。
【数学ⅡBC】
・試行調査と同じく第7問までの出題となりましたが、試行調査で出題されていた「平面上の曲線」の問題は含まれず、第7問は「複素数平面」のみの出題となっています。次回以降も同様の出題になるとは限らず、両単元の対策が必要になると思われます。
・具体的な身の回りの現象に関する計算に常用対数を利用する問題や、抽象的な関数について考察する微積分の問題など、分野も形式も多岐にわたる出題となりました。今後もさまざまな問題に対応できるような、十分な基礎力が求められる出題が続くとみられます。
【物理】
・前年同様、グラフを用いて解答する問題や、公式の成り立ちに関する出題が目立ちました。
・目新しい問題設定は減りましたが、立式や計算に工夫を要する問題がみられました。
・基本事項を確実に理解した上で、問題設定にあわせて論理的に思考し、工夫して正解を導き出す力が今後も求められると予想されます。
【化学】
・新課程での「エンタルピー」に関する問題が1問だけ出題されましたが、他の形式は前年とほぼ同様でした。
・計算問題ではやや長めの説明文を読む必要がある問題が多く、さらに典型問題とは少し異なる部分が随所にみられました。
・知識面でもやや細かい内容を問う問題がみられ、総合的にかなり難化しました。次回以降は難易度がある程度調整されると思われますが、様々な出題に対応できるよう問題演習を積み重ねて、準備をしておく必要があります。
-----------------------
令和7年度大学入学共通テスト
▶試作問題『数学Ⅰ,数学A』及び試作問題『数学Ⅱ,数学B,数学C』の概要
▶試作問題『数学Ⅰ 数学A』
▶試作問題『数学Ⅱ 数学B 数学C』
*************************************
■国語
※試験時間:80分から90分に増加(それでも時間不足になる可能性大)
○「現代文」
近代以降の文章が1問追加。第1問「評論」、第2問「物語文」、第3問「実用的な文章」(110点)
○「古文・漢文」
1問(45点)、漢文1問(45点)
試験時間は10分増えたが、引き続き時間的余裕はない。
「実用的な文章」問題では資料を読み取る力や情報処理能力が試されるため、旧来型の読解問題とは異なる処理速度が求められる。
古文・漢文の出題傾向はあまり変わらないと思われるため、「古典」を素早く解いて時間を稼ぐことも必要になる。
🔽実際の主題内容について
新課程になって初の共通テストでしたが、昨年の平均点116.5点を大幅に上回り、東進の集計では126.13点、河合塾の集計では126.82点の平均点が出ています。
共通テストになってからは低めの平均点で推移していましたが、久しぶりに平均点が120点を超えた年となったことで、各予備校も「易化」したとの分析を出しました。
まず、全体的に時間と配点が変わり、新しく「実用的文章」として第3問が加わっています。
【時間】80分→90分
【配点】
第1問 (評論)45点
第2問 (小説)45点
第3問 (実用的文章)20点
第4問 (古文)45点
第5問 (漢文)45点
第1問の評論は高岡文章「観光は『見る』ことである/ない-『観光のまなざし』をめぐって」からの出題で、内容は分かりやすい文章でしたが、設問がやや紛らわしいものが多かったかもしれません。
しかし、設問数自体が例年の5つから4つに減っていたため、じっくり考える時間を確保できたと思います。
第2問の小説は、出典が詩人でもある蜂飼耳の小説『繭の遊戯』であるため、比喩表現がやや多く、得手不得手が分かれたのではないでしょうか。ただこちらも設問が5つから4つに減ったため、読み取る時間は確保しやすかったと思います。
第3問の実用的文章は、以下の3つの資料からの出題されました。
・資料Ⅰ 外来語に関する意識調査の問題
・資料Ⅱ 「インフォームドコンセント」の言い換えの提案
・資料Ⅲ 外来語に関する意識調査の比較
全体的に試作問題よりも易化している印象ですが、複数資料の解釈問題は共通テストになってから徐々に増えてきたものの、新課程からはこのように別途専門枠が作られたため、今後難化が予測されます。
第4問の古文は、『在明の別』と『源氏物語』若菜下の巻からの出題でしたが、『源氏物語』が設問に関わったのは1題のみで、残りはすべて『有明の別』からの出題です。しかもリード文と選択肢から本文の内容がある程度類推でき、設問も5つから4つに減りましたので、古文はかなり易化した印象です。
第5問の漢文は『論語』の一節、 皆川淇園『論語繹解』、田中履堂『学資談』と複数からの出題でしたが、内容・難易度は例年通りです。ただ、こちらも設問数とマーク数が減っている為、負担は軽くなったのではないでしょうか。
以上のことから、全体としては易化し、傾向としても概ね予想通りの共通テストとなりました。
-----------------------
▶試作問題「国語」の概要
▶試作問題
*************************************
■外国語
※1科目選択(英語は別途リスニング試験あり)
○「英語」
※英語リーディング・その他外国語:80分
※英語リスニング:60分(解答時間:30分)
※配点:200点(英語はリーディング:100点・リスニング:100点)
<大問数>
旧課程の6から新課程では8へ
<大問の構成>
新課程 第1問 6点 = 旧課程 第1問B
新課程 第2問 10点 = 旧課程 第2問B
新課程 第3問 9点 = 旧課程 第3問B
新課程 第4問 12点 = 旧課程になし(試作問題 第B問)
新課程 第5問 16点 = 旧課程 第4問
新課程 第6問 18点 = 旧課程になし(試作問題 第A問)
新課程 第7問 15点 = 旧課程 第5問
新課程 第8問 14点 = 旧課程 第6問B
<語 数>
2024年度(旧課程) 約6,200語
2025年度(新課程) 6,700~6,900語(予想)
○「ドイツ語」
○「フランス語」
○「中国語」
○「韓国語」
※各200点・80分
英語:全体としては大きな変更はないものの問題量や総語数も増える傾向にあるため、引き続き4技能の中のリーディングとリスニングの処理速度が求められる。
一例として以下の試作問題(リーディング)に「リーディングの問題でありながらライティングを意識させるよう工夫を凝らした」問題も含まれているため、要チェック。また、本文や図表の内容が読みとれることを前提にそれらの要旨や追加的・推論的な内容、更には複数のテキストの整理能力や比較・関係が問われる。
🔽実際の主題内容(英語)について
英語(リーディング)
新課程移行後、初の共通テストでしたが、昨年の平均点51.54点から6点強上回り57.69点でした。各予備校も「やや易化~易化」という分析を出しています。
昨年と比較すると大問数は2つ増え、全8問であった一方で、設問数は6つ減少、マーク数も49から44と5つ減少しました。また、問題本文や図表、選択肢全てを含めたワード数は約5,680語であり、昨年と比較して約700語減少しました。
例年のように1つの大問の中でA,Bに分かれている問題は消滅し、正解を選ぶのに物議を醸すレベルの紛らわしい問題も見られず、全体的に受験生にとって取り組みやすかったのではないでしょうか。
また、新課程へ移行するにあたり、Writingを念頭においた問題も出題されました。
与えられたテーマについて、文章の論理構成に注意して訂正する問題や、提示された立場のエッセイを作成する為に、複数の資料を読んで論拠を整理する問題等がそれに当たります。この類の問題は今後も出題されていくでしょう。
また、第3問及び第4問以外の全ての大問において、図や表、イラストが用いられた問題が出題されました。これは、複数の様々な情報ソースから要点や論点を把握する力、そして論理強化材料として必要な情報を読み取る力を問うことを狙いとする大学入試センターの試験作成方針に則っており、この傾向は今後も続くと考えられます。
【試験時間】80分
【配点】 *=読解表現融合問題
第1問 パンフレット 6点 (マーク数3)
第2問 ブログ記事 12点 (マーク数4)
第3問 物語文 9点 (マーク数6)
第4問 エッセイとコメント推敲* 12点 (マーク数4)
第5問 eメールのやりとり 16点 (マーク数6)
第6問 物語文 12点 (マーク数8)
第7問 論説文 16点 (マーク数6)
第8問 複数の意見と資料* 17点 (マーク数7)
第1問(標準)
これまでA,B2つの問題で構成されていましたが、今年は1問題でした。
初心者が魚を飼う際の注意点等を4つのイラストから読み取るもので、基本レベルの問題ではあるものの、イラストをよく見て選択肢を選ぶ必要がありました。
第2問(やや易)
第2問も昨年まではA,Bの2つに分かれていましたが、今年度はBタイプの問題のみで設問数は1問減少し4問になり、語数も約130語減少しました。
英国人作家による「空を飛ぶ乗り物」についてのブログを読んで問いに答える問題で、意見を問う問題も出題されました。読みやすいテーマであるものの、問2の言い換え問題は本文と選択肢の表現のギャップが大きく戸惑った受験生もいたかもしれません。
第3問(やや易)
第3問も昨年まではA,Bの2つに分かれていましたが、今年度はBタイプの問題のみ、設問数も2問減少し6問になりました。内容は「コンテストでのバンドの失敗と反省」についての物語文で、問1は物語の筆者を選ぶ新形式の問題、問2は昨年まで第5問(伝記問題)の問1で問われた時系列に沿って選択肢を並べる問題でした。選択肢の一部にやや紛らわしいものがありましたが、苦戦するほどではなかったと思われます。
第4問(標準)
大学入試センターの「試作問題B」と同系統の問題でした。「スローライフ」について自分の書いたレポートに対する教師のコメントを踏まえて、推敲し適切に訂正する力を見る4つの問いから構成されています。パラグラフの論理構成や論理展開を正確に把握できれば正解できる標準問題でした。
第5問(やや易)
「ローカルビジネスに関する会議」について、学生と教授のメールのやりとりを読み5つの問いに答える問題でした。学生、教授いずれか、もしくは両方のメールや添付された図表のうち、どの部分に解答の根拠があるのかを判断し解答していくもので、各情報ソースを効率的に把握する力が試されました。また、メール内容から推論して答える問題も昨年同様、出題されました。
第6問(やや難)
「スーパーヒーロー」についての物語を読み、それに対する感想メモを完成させる問題でした。昨年の本文と比べて約260語減少しました。昨年同様、物語は時系列順に書かれておらず、それを整理しながら順序よく読み取れるかが鍵となります。
同時に、明確に描写されていない登場人物の相関関係を把握する必要もあり、解答に時間がかかった受験生も少なからずいたのではないでしょうか。
第7問(標準)
昨年までの第6問と同系統の問題で、「動物の睡眠パターン」に関する記事を読み、口頭発表の為の要点について6つの空欄を埋めるものでした。本文にはやや難解な科学用語が含まれていたものの、概ねパラグラフに出てくる順序で設問が構成されていた為、解答を導き出すのはさほど困難ではなかったと思われます。
第8問(標準)
「試作問題A」での出題と同系統の新傾向の問題で、「宇宙開発」に関する5人の意見と資料を読み、3つのステップに沿ってエッセイのアウトラインを組み立てていくものでした。立場の異なる5人の意見を読み、それぞれの論点を理解するステップ1、自分の意見を支持する2人を選んでその共通点を答えるステップ2、複数の資料から自分の意見の根拠材料を判断するステップ3という3つの段階を踏んでいく中で、複数の情報をもとに論点を整理し判断する力が問われました。
全体的な語数は450語と多めである一方、各センテンスは短めで読みやすく、設問に対する該当根拠を特定するのにさほど苦労しなかったと思われます。
-----------------------
▶試作問題「英語」の概要
▶試作問題(リーディング)
▶試作問題(リスニング)
参考
▶2024年度のリスニング問題
*************************************
■地理歴史 ■公民
※6科目から最大2科目選択(1科目:100点)
※1科目60分 2科目:130分(解答時間:120分)
地理歴史
○「地理総合・地理探究」
難易度はかなり上がると予想される。
○「歴史総合・日本史探究」
難易度は従前通りだが資料の読み取り速度や類推力が求められると思われる。
○「歴史総合・世界史探究」
難易度は従前通りだが、こちらも資料の読み取り速度や類推力が求められそうだ。
○「地理総合-歴史総合-公共」(何れか2科目の内容を選択)
公民
○「公共・倫理」
○「公共-政治・経済」
難易度は変わらないものの、やはり読解力と処理速度が重視される傾向にある。
※2科目選択時の不可事項
「公民」2科目の選択は不可
「地理総合・歴史総合・公共」で選択した科目と同一名の科目の組み合わせは不可。
例①:「歴史総合・日本史探究」と「公共・倫理」、「地理総合・地理探究」と「公共、政治・経済」のような組み合わせは可。
例②:「歴史総合・日本史探究」、「歴史総合・世界史探究」の2科目選択は可。
公民の「公共・倫理」、「公共-政治・経済」の組み合わせは不可。
※「地理総合-歴史総合-公共」を選択する場合の留意点
所謂旧帝大(北海道大、東北大、東京大、名古屋大、京都大、大阪大、九州大)や難関大学の中には「地理総合-歴史総合-公共」科目を選択できないケースあり。
▶試作問題「地理歴史」の概要
▶試作問題「公民」の概要
▶科目別試作問題
*************************************
■理科
※5科目から最大2科目選択(1科目:100点)
※1科目60分 2科目:130分(解答時間:120分)
※同じ時間帯の中で1-2科目を選択
○「物理基礎-化学基礎-生物基礎-地学基礎」(何れか2科目の内容を選択)
○「物理」
○「化学」
○「生物」
○「地学」
物理:大きな変更はないと思われる。
化学:「熱化学」に変更があり、その他の単元でも細かい変更があると思われるが、理科は全体的に従前通りの対策で問題ないと予想される。
*************************************
■情報Ⅰ
※新設科目
※100点(60分)
出題内容
情報社会の問題解決
情報通信ネットワークとデータの活用
コミュニケーションと情報デザイン
コンピュータとプログラミング
次々に解いていかないと時間不足になる可能性大。兎にも角にも問題傾向に慣れておくことが肝要。
▶試作問題「情報」の概要
▶参考問題
*************************************
大学入試センターウェブサイト
▶令和7年度試験の問題作成の方向性、試作問題等
※試作問題の概要・試作問題・正解表あり
▶令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの問題作成方針に関する検討の方向性について
▶令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの出題教科・科目の問題作成方針に関する検討の方向性について
▶2022~2024年度(令和4年度~6年度)の過去問
*************************************
■主な私立大学の状況
○早稲田大学
政治経済学部・国際教養学部・スポーツ科学部では既に共通テスト利用が必須ですが、2025年度入試からは社会科学部と人間科学部も共通テスト利用が必須となります。
○上智大学
TEAP、共通テスト利用受験以外は必須
○立教大学
英語民間試験利用以外は共通テスト利用必須(※文学部以外)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■2024年度の共通テストについて
2024年度の 共通テストの全体傾向は前年同様でしたが、平均点は英語(R)、「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」、「日本史」で下がり、「英語(L)」と「国語」、「生物基礎」、「地学」、「地理B」は上がる予想です(5教科7科目(900点満点)の平均点は文系、理系共に上昇する見込み)。
当社でも特に英語(R)で苦戦した生徒さんが一定数おりましたが、今回は得点調整なしです。出題者側も毎年トライアル・アンド・エラーを繰り返しており、共通テスト自体がまだ未成熟な段階にあることも窺えます。
▶平均点(大学入試センターの中間集計)
さはさりながら条件は皆同じであり正に勝負はこれからですので、各大学のボーダーライン(
河合塾・
バンザイシステム・
駿台Benesse
)や大学の特色が出る個別学力試験(2次試験)の方式、配点比率、勝負する選択科目などをしっかり見定めた上で志望大学合格を是非とも勝ち取っていただきたいと思います。
【英語R】
難易度:昨年並かやや難化(英語Lはやや易化)。
昨年度より英文語数は300語程度増加したものの、出題形式は昨年同様、大問6題から構成され、また、設問数、マーク数も昨年と同じであり、出題傾向、難易度共に昨年並。
今年度も、大問2のB以外の問題については英文テキストに加え、グラフ、表、図、イラストが使用され、様々な情報から概要や要点を把握させるという出題の趣旨は一貫して変わっていない。
ただ、今年度の大問2のレビュー記事の読み取り問題では、本文に述べられていないものを選択する問題や、大問3のブログ記事や学校新聞の記事の読み取り問題では、英文を理解した上で時系列を整理し並び替える問題や、本文を基に正しい情報を推測する問題等、受験生の思考力や判断力が求められる問題が出題された。
大問5では物語文の読み取り問題が出題されたが、本文の語数は昨年に比べて300語増加した中で長大な文章の時系列を把握することに戸惑った受験生も少なくないのではないか。恒例の簡単な計算問題もこの大問5で出題された。
【数学】
数学ⅠA
難易度:難化。
電柱と影の問題やマラソンの厚底靴の登場とタイムについての問題など日常生活を題材にした問題解決能力が問われるものが出題された。
数学ⅡB
難易度:やや難化。
数列であまり見慣れない漸化式が出題された。
回りくどい説明文の分量は以前より減ったものの、目新しい題材や形式の設問がやはり多くみられた。
来年度からの共通テストでは出題単元が追加・再編されると共に、上記の傾向も続くと予想されるため、共通テスト専用の対策が必須となる。
【国語】
難易度:やや易化。
平均点は10点以上上昇する見込み。
第1問は2004年にも出題された渡辺裕の文章で、王道の芸術論かつ良問揃いと言える。問6は生徒の書いた文章の推敲という、今までにない視点からの出題だったが、本文を踏まえれば決して難しい問題ではない(当社の生徒さんの多くは全体的に取り組みやすかったという印象を持ったようです)。
第2問は語句問題が復活し、本文には「演技」という受験生に馴染みの薄いテーマが出題された。問7には演出家の太田省吾の文章が出され、やや深い考察が必要とされる。こちらは第1問に比べればやや難しく感じると思われる。
第3問の古文は江戸時代の擬古文のため、本文は読みやすかったと思われる。語句は重要古語がそのまま出されたため、ここは落としたくないところ。
他の設問も含めると、難易度はやや易化したと言える。
第4問の漢文は、非常に美しい漢詩の問題であり、形式に関する問題と、返り点や書き下し文など、毎年出ている文法問題が出題された。
漢文は例年より易しかったので、ここで点を稼ぎたいところ。
全体的にはオーソドックスな問題が多く、かつてのセンター試験の形式に近づいた印象。
【物理】
難易度:昨年並かやや難化。
探究活動を意識した見慣れない問題や実験多し。
ペットボトルロケット、弦の問題あり。
【化学】
難易度:昨年並かやや易化。
日常生活を題材にした問題が多く出題された(医薬品、質量分析法、ドーピング、実用電池、冷却剤など)。
物理、化学共に平易にみえても、基本事項の確かな理解が無ければ正解に至れない問題が多くみられた。
あるテーマを中心に、複数の単元にわたる内容を含む大問があり、柔軟な発想が必要となる。
また、実験データの読み取りに関する出題が増加したため、数式とグラフの対応を考える問題への対策が必須である。
-----------------------
2021年に初めて実施された共通テストでは、「英語民間試験の活用(英語外部検定利用入試)と数学、国語の記述式問題の導入」が見送られました。
※2021年夏時点では少なくとも2025年1月実施の共通テスト以降も英語外部検定利用入試及び記述式問題の出題が事実上見送られること、新学習指導要領の教科・科目の再編に対応するため、共通テストを現在の6教科30科目から「情報」を新設した7教科21科目に再編されることが確定しています。
「情報」に加えて2022年度から新しい学習指導要領が適用される「数学」の動向にも留意する必要があります(詳細は
▶家庭教師と学ぶ数学
をご覧ください)。
教科・科目の再編理由は地域格差や経済格差に加え、50万人以上が受験する中で公正な採点体制の確保などの課題を克服できないというものですが、こんな当たり前の結論を出すのに有識者会議なるものを何度も開催してきたわけで、このような体たらくでは有識者の名が泣くのではないでしょうか。
名ばかり「ゆとり教育」の大失敗に懲りない文科省も文科省ですが、元来有識者は「国家百年の計は教育にあり」ということを心得ている方々でなければなりません。様々な分野で不可解な有識者会議が尤もらしく開かれていますが、教育、大学入試の分野にまで大人の保身と責任のなすりつけ合いを持ち込むことはやめてもらいたいものです。
何れにせよ「暗記だけでは解けない思考力・判断力・表現力」を測るものに出題形式が変わっていくとしても、基本事項を正確に理解していることがベースになることに変わりありません。
そもそも共通テストがいかなる形式で出題されるにしても、例えば難関国立大学の2次試験のようになるわけもなく、要は確かな基礎力と標準的な思考力があれば、十分に対応可能だと言えます。
今後も共通テストの実施方法については暫く試行錯誤が続くことになります。
しかし、英語のリスニングの配点比率が変わろうが(配点比率は大学によって大きく異なるため最新情報を確認する必要があります)、リーディングの単語量が多少増えようが、出題傾向が変わろうが、数学の問題で読解力が試されようが、国語で日常のシーン(実用文)に関する判断力を問われようが、マーク方式に複数選択や正答なしを選択するマーク形式が追加されようが、正しい学習方式に基づいて「真の学力」さえ身につけることができれば恐るるに足らずです。
▶ 目次へ戻る
家庭教師アルファ・ネクサスのプロ家庭教師は着実に基礎力を養成すると共に思考力、柔軟な応用力を身に着けさせる独自のメソッド(例えば ▶【家庭教師と学ぶ英語】・
▶【英語ワンポイントアドバイス】や
▶【家庭教師と学ぶ数学】・
▶【家庭教師と学ぶ国語】
)を持っており、それらを常に生徒さんの習熟度に合わせて駆使しています。
従って最新の情報に基づいた共通テスト対策はもちろん、東大、京大をはじめとする旧帝大ほかの国公立大学2次試験記述対策から、早稲田、慶應などの超難関私大の記述対策、上智、明治、東京理科、青山、立教、中央、法政、学習院ほかの難関私大の一般入試や総合型選抜(AO入試)、推薦入試まで柔軟に対応することが出来るのです。
▶AO入試・推薦入試対策・小論文対策
については大学別にサポートしています。併せて
▶内部進学対策(一貫校フォロー)
も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
大学受験の小論文指導は、当社
▶大学生向け家庭教師コース (
▶特別コース内 )で卒論や大学生のレポート指導に当たっているプロ家庭教師が担当いたします。
大学受験を知り抜いた家庭教師が現役高校生から浪人生、大学再受験生それぞれの状況に応じた合格プログラムを作成し、生徒さんを毎年志望大学合格まで導いていますので、まずは
▶無料体験授業でその実力をお試しください。
➡『Q&A』
➡『当社の誇り』
-----------------------------
▶ 目次へ戻る
大学受験のプロってどんな人?
家庭教師アルファ・ネクサスには独自の人脈を活かした「他社には在籍していない高レベルのエキスパートである「▶プロ家庭教師、厳選学生 」が多数在籍しています。大学受験を熟知した担当家庭教師と当社の教育コンサルタントが学校や学年、習熟度に応じて指導プランを決定。
基礎力の養成はもちろん、定期テスト、内部進学、推薦入試対策、総合型選抜(AO入試)対策も万全に行います。
大学入試問題の作成経験や有名中高一貫校での定期試験問題作成経験のある家庭教師など、豊富な経験と多くの大学合格実績を持つエキスパートが指導に当たる他、ご希望に応じて厳選学生教師、医学部生を派遣することも可能です。
家庭教師アルファ・ネクサスと当社の家庭教師は、受験生の皆さんに、日本の大学入試の良き点を吸収し、更には国際バカロレア(IB)や本当の意味でのリベラルアーツ教育にも順応できる学生、真に独立した主権者として、日本と世界に貢献し、リーダーたり得る人、そして常に感謝の心を忘れない謙虚で強靭な精神を持ったスケールの大きな大人を目指していただきたいと願いながら大学受験の全てに対応すべくサポートと授業を実施しています(▶当社理念)。
※当社では大学受験生向けに ▶オンライン(インターネット)授業コース もご用意しております。
▶在籍教師 一覧には大学受験を専門とするプロ家庭教師や厳選大学院生のプロフィールが多数掲載されています。当社の家庭教師は、東京大学ほかの旧帝国大学をはじめとする難関国立大学、早稲田大学、慶應大学、上智大学、明治大学、東京理科大学ほか多くの難関私立大学や医学部の豊富な合格実績を持っています。
例えば駿台、河合塾ほかの予備校に通う生徒さんには、予備校での学習フォローをしっかり行いつつ、習熟度や性格、今までの学習環境、ご希望に応じた個別合格プログラムを作成。生徒さんごとに最大限の効果を発揮できるようにサポートし、結果を出しています。
当社の家庭教師は、予備校等をやめてしまったり、自宅で浪人生活を送っている、或いは▶不登校中の生徒さんの強い味方になってくれます。不登校の生徒さんも高認(高等学校卒業程度認定試験・旧大検)の取得段階からサポートし、今まで何人も大学合格まで導いてきました。
当社では生徒さんの実力・個性に応じて個別カリキュラムをしっかり組んで学習を進めていくため、大学受験専門の家庭教師だけで大学合格を果たしたケースやプロ家庭教師が一つのチームとして有機的に連携することで、総合偏差値30台から偏差値60台後半(河合塾の偏差値基準)にまで引き上げ、志望大学に合格したという▶ドラマチックなケースも複数存在します。
●また、トップページにある「▶大学入試過去問解説」ページでは当社の家庭教師兼アドバイザーが大学入試の過去問(数学)を動画で解説していますので、併せてご覧ください。
家庭教師を派遣する会社の中には直接契約サイトから家庭教師のみを派遣したり、或いはアフターフォローがほとんどなされない会社もありますが、当社では無料体験授業時から家庭教師と教育コンサルタントが密接に連携して『▶家庭教師派遣後のアフターケア』もしっかりと行っていますので、ご安心ください。
授業料もリーズナブルな設定となっています。例えば大手各社(いわゆる相場)と比較していただければおわかりになるかと思いますが、同じご予算でしたら1クラス上の大学受験専門のプロ家庭教師を派遣することが可能です。また、当社は【入会金・違約金なし】及び【完全後払い制】を採用していますので、過払い等も一切発生いたしません(【費用その他内の
▶料金システム 】をご覧ください)。
➡『お問合せ』
-----------------------------
▶ 目次へ戻る
大学受験のプロを活かす独自のチーム対応とは?
家庭教師アルファ・ネクサスでは、複数の家庭教師と教育コンサルタントが連携する「 ▶大学受験に特化したチーム制
」も採用しています。
理系科目と文系科目で、それぞれ別の家庭教師を派遣したり、より劇的な効果を求めて複数の家庭教師を派遣する場合、一般的な家庭教師センターでは指導に関する情報はそのセンターに集約されるだけで、教師間で連絡をとりつつ連携することはほとんどありません。
当社はプロ家庭教師が「チーム」となって大学受験を成功させることも得意としています。保護者様とも常にコミュニケーションを取りながら生徒さんの大学受験を全力でバックアップし、教育コンサルタントがしっかりチームを統括します。これにより、指導に関することだけではなく、ちょっとした体調や心の変化などについても可能な限り情報をすべての家庭教師と共有し、学習効果を高めています。
また、共有した情報は、随時保護者様にメールや電話でお伝えしています。
※当社では▶毎月必ず家庭教師からのコメント(授業の進捗状況やアドバイス等)をメールでお伝えしています。同時に教育コンサルタントが、生徒さんと直接お話して学校や予備校他のことや志望大学、学部、将来の職業など進路に関する相談に乗ったり、励ましたり、時に上手に叱るなどして側面からサポートしています。
このような形でチームワークが有機的に機能することで、揺るぎない信頼を保護者様や生徒さんから得ることができていることも、当社が誇りとするところです。
また、必要に応じて各ご家庭ごとに担当家庭教師同士が直接連絡を取ることもあります。このように▶同じ会社から複数のエキスパートを派遣し、連携させることができるのも当社の強みです。
-----------------------------
▶ 目次へ戻る
直前対策・予備校や塾に頼らない浪人対策
予備校や塾には通っていない、或いは不登校や自宅浪人ほかのケースでも、生徒さんの実力・個性に応じて個別カリキュラムをしっかり組んで学習を進めていく為、家庭教師だけで中高一貫校をはじめとする高校のフォローはもちろん、大学受験を成功させたケースも数多くあります。
■再起に向けた浪人生対策
やむを得ず浪人することになってしまった生徒さんは、来年こそは志望大学に絶対合格すべく、是非とも頑張っていただきたいと思います。
当社の家庭教師は浪人を決意したその時から数学、英語、国語、理科、社会など全ての科目において、まずは今までの学習方法が正しかったのか、効率良く学習できていたか、参考書や問題集選びは適切であったか等々を徹底的にチェックし、毎年リベンジ合格のお手伝いをしています。
予備校や塾のカリキュラムは万人向けである集団授業を前提にしている為、どうしても固定化せざるを得ない面があります。従って過去問対策などの個別対策も手薄になってしまうと同時に生徒さんに合わせた臨機応変な対処もできません。
もちろん模試の実施やライバルが目の前にいる集団授業には緊張感があるなど予備校ならではの良さはありますが、「浪人したら予備校に行くのは当然」という固定観念ありきですと陥穽にはまることも危惧されます。
浪人生が予備校を選ぶ理由として考えられるのは例えば、
・他に在籍ができるところがないし何となく安心だから
・友達も行くし周りもすすめるから
・現役生の時も通っていたから
などといったあまり積極的でない理由が並びます。
現役生の時と同じようなことを漫然と続けてしまったり、予備校に通っているだけで何となく「頑張っている受験生になった気分」にさせられてしまい、一向に成績が上がってこないといった事例は枚挙に暇がないと言えます。
当社の家庭教師は一方通行の集団授業では手が回らない分野である「習熟度に応じたオリジナルの学習プログラムの立案と効率的且つ臨機応変な浪人生向けの個別対策」を軸に浪人生を徹底サポートし、個人の能力を最大限に発揮できるよう最適化を図っていきます。
※予備校などの浪人生向けのカリキュラム例
4~8月 :基礎固め
9~12月:応用問題演習(但し基礎固めが終了していない場合は消化不良になる恐れあり)
1月~ :過去問演習(生徒側が自主的に実施することが前提であり、予備校側は基本的に質問対応のみ)
というような流れが一般的です。
※当社の浪人生向けカリキュラム例
予備校などの講義が始まるのは基本的に4月中旬以降です。当社の家庭教師の授業では状況に応じて浪人が確定した時点から(早いケースでは2月中旬頃から)徹底したサポートを実施しているため、予備校などに比べて1ヶ月半から2ヶ月程度も早く効率的な学習を開始できるという大きなアドバンテージをスタート時点から得ることが可能となります。
●得意な科目については、
3~7月︰お手持ちの参考書類が適切か否かを判断。適切な場合は習熟度に応じてよりハイレベルな問題集等を選別の上そちらも活用して計画的に演習を進める。
単元によっては一旦基礎に立ち戻ったり、逆に過去問レベルの問題演習に早めに着手する。
必要に応じて家庭教師が豊富な経験に則して用意するオリジナル厳選問題や予備校のテキストなども活用する。
8~11月︰過去問演習を積極的に取り入れながら、既習内容を定期的に確認し定着を図る。
12月~本番︰過去問の本格的な演習計画を立ててそれを実行し、合格する答案の書き方や時間配分のチェック、論述問題の添削など、きめ細かい実戦的な対策を行う。
●苦手な科目については、
3~8月︰こちらもお手持ちの参考書類が適切であるか否かをチェックし、最適な参考書類を活用しつつ基礎からじっくりと解説し、苦手意識をなくした状態で応用レベルに進む準備を整える。
必要に応じて家庭教師が豊富な経験に則して用意する基礎から鍛え上げることができるオリジナル厳選問題も活用する。
9~12月︰ハイレベルの問題集に適宜移行しつつ演習を進め、少しずつ過去問に近いレベルの問題が解けるよう演習を進める。
1月~本番︰志望校の過去問を十分に研究して、効率よく合格点を取るために強化すべき単元や時間配分を確認し、実戦的な対策、1点でも多く取れる答案の書き方対策を徹底的に行う。
---------------
何れの場合もまずはゴールデンウィークまでにどこまで仕上げることができるか、夏までにライバルにどこまで差をつけられるかで、その後の成績も変わってきますので、浪人生として再起を図ることになったからには一刻も早く適切な学習計画にそって勉強に励んでいただきたいと思います。
当社では科目別に複数のプロ家庭教師がチームを組むことで、いわゆる宅浪生(自宅浪人生)に対するリベンジ合格のお手伝いもしており、予備校や塾に頼らずに家庭教師の授業だけで毎年多くの自宅浪人生を志望大学合格に導いています。
また、受験まであと2,3カ月しかないなど、通常の方法では間に合わないようなケースでも、独自の直前対策を講じて結果を出しています。諦める前に、一度ご相談ください。
-----------------------------
▶目次へ戻る
予備校他のフォロー
予備校や塾に通う生徒さんについてはそこで使用しているテキストを使用しつつ、予備校・塾では手が回らない部分までしっかり個別にサポートすることが可能です。
例えば駿台や河合塾での講師経験を持つ家庭教師が生徒さんの習熟度に応じ、効率的に学習フォローを進めていきます。
受験直前期には志望大学の過去問対策を徹底的に実施。大学受験に精通したエキスパートにしか作成できない合格プログラムとその指導力を是非とも体験してみてください。
-----------------------------
▶ 目次へ戻る
Contact Us
会社連絡先
住所
■ 本社オフィス
▶東京都中央区日本橋本石町2‐1‐1
アスパ日本橋オフィス
受付時間:
10:00-22:00
電話:
03-5389-3995
E-mail:
info@alpha-nexus.jp
お問合せフォーム
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。